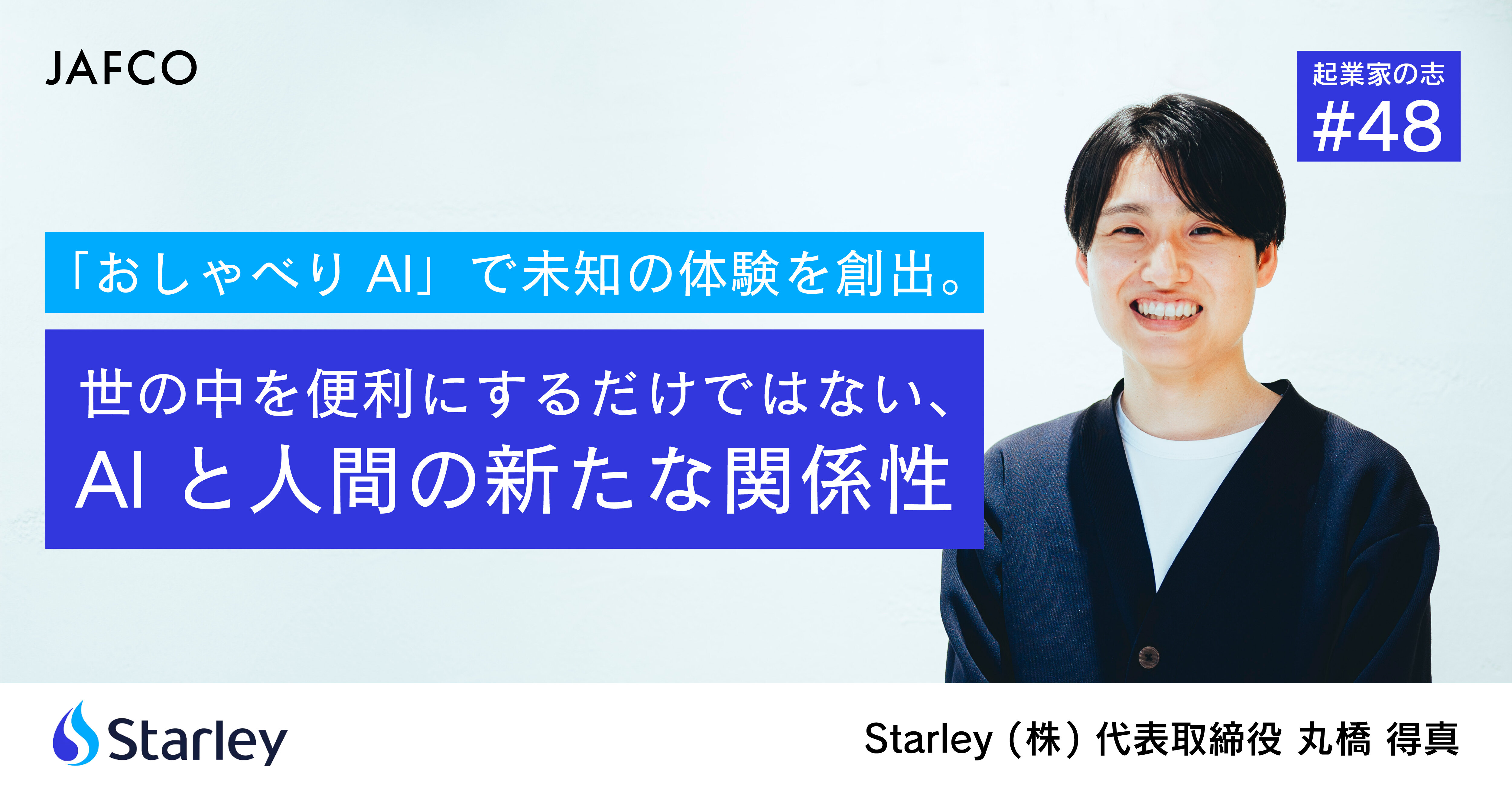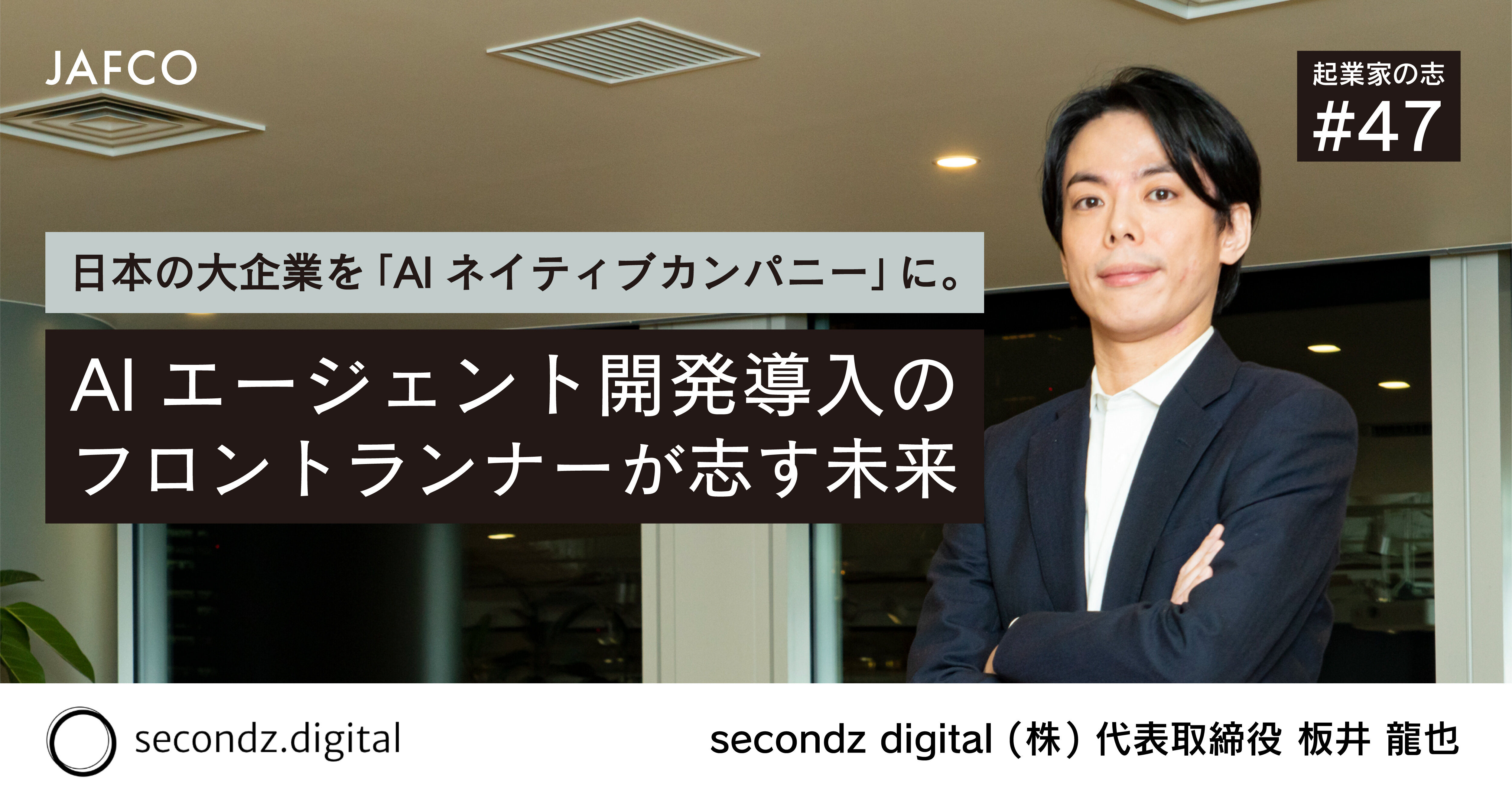起業を決めた背景や、事業が軌道に乗るまでの葛藤、事業を通じて実現したい想いを聞く「起業家の志」。
第49回は、株式会社Arrowsmith 代表取締役の安藤弘樹氏に登場いただき、担当キャピタリスト小林泰良からの視点と共に、これからの事業の挑戦について話を伺いました。

【プロフィール】
株式会社Arrowsmith 代表取締役 CEO CScO 安藤 弘樹(あんどう・ひろき)
博士(医学)。大阪大学大学院で博士号を取得後、国立国際医療研究センター 感染症制御研究部、マサチューセッツ工科大学 合成生物学センターにて研究員/上級研究員として従事。2017年に岐阜大学大学院 医学系研究科 助教、2020年に特任准教授に就任。2020年にアステラス製薬株式会社 次世代ファージセラピー研究ユニット Principal Investigator、2024年にユニット長に就任後、2025年2月に株式会社Arrowsmithを設立。
【What's 株式会社Arrowsmith】
細菌に感染するウイルス「バクテリオファージ」を活用して細菌感染症を治療する「ファージセラピー」に着目し、自然界に存在するファージを改変して薬剤として利用するための人工合成プラットフォームを開発。抗菌薬が効かない薬剤耐性菌による感染症が世界的に拡大する中、改変型ファージセラピーの社会実装を志す。特に、緑膿菌肺感染症での薬剤耐性菌が問題となっている嚢胞性線維症患者に向けた治療薬の開発を目指している。
2050年に世界最大の死因となる感染症を「人工ファージ」で解決する
ーArrowsmithが実現に向けて取り組んでいる「改変型ファージセラピー」とはどのような治療法ですか。
安藤 「ファージ」というのは細菌に感染する天敵ウイルスのことで、これを活用した細菌感染症の治療法を「ファージセラピー」と言います。ファージセラピー自体は100年以上前から存在するものですが、ペニシリンが発見され抗菌薬が治療に使われ始めてから、下火になっていました。ところが、近年、抗菌薬が効かない「薬剤耐性菌」による感染症が蔓延し、世界的な問題になっています。2050年には年間1,000万人が薬剤耐性菌感染症によって亡くなるという予測もあります。このような背景からファージセラピーが再注目されているんです。
ファージは自然界に存在するウイルスで、従来のファージセラピーは天然のファージを使うのが当たり前でした。そんななか、ファージを合成生物学的アプローチによって改変し、新たな機能を付加する方法を研究していたのが、私のMIT(マサチューセッツ工科大学)研究員時代のボス(Prof. Timothy Lu)でした。ただ、当時改変できたのは遺伝学的な手法が確立されているごく一部のモデルファージだけでした。そこで、ファージセラピーへの応用を見据えて、モデルファージだけではなく様々な種類の天然ファージを改変できる初代汎用改変プラットフォーム(yeast platform)を私が開発しました。また、日本へ戻ってから二代目のプラットフォーム技術(synthetic engineering platform)を開発しました。ここから創り出す機能性を付加した人工ファージ(synthetic phage)を活用し、深刻化する薬剤耐性菌問題を解決していくことが当社の目標です。
ー安藤さんがファージセラピーの事業化に取り組むようになった背景には、どのようなきっかけがあったのでしょうか。
安藤 私は博士課程で腸管出血性大腸菌O157 Sakai株の基礎研究をしていました。あるとき、O157 Sakai株の全遺伝子の発現量を解析していたのですが、その際にゲノムの中に多数のプロファージ(活動を休止して眠っている状態のファージ)やファージゲノムの残骸があるのを目の当たりにしました。
O157 Sakai株が多数のプロファージを持つことや、ファージが細菌に感染することはもちろん知識として持っていましたが、「目で見て実感した」ことは大きな体験でした。この瞬間、私が思いついたのは「薬剤耐性菌感染症をファージで治療できるのではないか?」というものでした。
「ファージセラピー」という名前まで考えて意気揚々としていたのも束の間、Webで検索したらすぐに「昔からある治療法」だと判明しました(笑)。
自分の無知を思い知りガッカリしましたが、このときの閃きの感覚、それは日々の研究活動における閃きの感覚とは全く異なるもので、それ以来ファージセラピーの研究がしたくて堪らなくなってしまいました。当時の指導教官に相談して、本来の研究の合間にファージ研究もさせてもらいました。
ーそのときの感覚が研究者魂に火をつけたのですね。本格的に研究するようになったのは?
安藤 2012年にMITへ行ってからです。当時、アメリカやヨーロッパではファージセラピーのスタートアップがいくつか立ち上がりつつありました。一方、日本ではアカデミアで基礎研究は進んでいましたが、産業化の動きはなかったように記憶しています。
MITで論文を書き、アメリカのスタートアップから「一緒にやらないか」とお声がけもいただきました。ただ、やはり母国である日本の科学に貢献したいという思いがあり、国内で起業する道を模索しました。2015年、一時帰国して「チームArrowsmith」として参加した『バイオサイエンスグランプリ』で最優秀賞をいただき、本格的に起業を目指しました。しかし、当時は全員基礎研究者のチームであり、経営面のハードルや私の力不足で実現には至りませんでした。
ーそこから2025年のArrowsmith設立までの間に、アステラス製薬に所属されていた時期がありますね。それはどのような経緯からでしょうか。
安藤 2019年の初め頃、ある企業の経営者からお誘いいただき再び起業する話が出ていました。私はCScO(最高科学責任者)として起業するつもりでいたのですが、ちょうど同じ頃に声をかけてくれたのがアステラス製薬でした。私のファージ改変技術を使って一緒に事業化を目指したいと言っていただきました。
ものすごく迷いましたが、潤沢な研究資金や製剤化・上市までのノウハウなどを持っていること、何より一日でも早いファージセラピーの実現を考えて、アステラス製薬と一緒に研究開発をすることにしました。
岐阜大学ファージバイオロジクス研究講座との5年にわたる共同研究により、ファージセラピーの事業化は大きく前進しました。研究成果をArrowsmithへ導出し、研究開発をさらに加速させます。
細菌感染症の分野でPhDを取得したキャピタリストがプロジェクト開始時点から会社設立に向けて 伴走
Arrowsmith安藤氏(右)、ジャフコ小林
ージャフコと初めて接点を持ったのはいつでしたか。
安藤 2019年の夏でした。その際は小林さんとは別の方からご連絡いただき、出資のお話というよりは、私の現状や今後の展開についてお話をした形でした。小林さんと最初にお会いしたのは2022年でしたよね。
小林 そうですね、直接お会いしたのはその時が初めてです。ただ、元を辿ると私のアカデミア時代のボスが安藤さんの博士課程時代の恩師と同門といった縁がありました。私も今から15年ほど前は東京大学で細菌感染症の基礎研究をしていたのですが、自分の専門性で論文以外に何か社会の役に立ちたいと考えを巡らせることがあり、その時に社会実装の機運がある技術領域の一つにファージセラピーがあると考えていました。
その後、複数の事業会社で異なる専門性・職種・業界を歩んだものの、2020年にジャフコのベンチャーキャピタリストに転身し、ジャフコのキャピタリストとして独り立ちをはじめた2022年頃に創設されたのがAMED(日本医療研究開発機構)の「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」でした。創薬スタートアップ投資の障壁となっていた企業主導治験の大きな費用負担が軽減できることもあり、ジャフコとしても積極的に認定VCへ申請して採択され、ソーシングに動き出していました。
本補助事業は当初、「感染症のワクチン・治療薬に関連する技術の実用化開発を行う創薬ベンチャー企業を支援する目的」で創設されたものの、感染症に取り組む創薬スタートアップは私の知る限り日本にほぼなく、そもそも感染症分野の国防に対する重要性に反し、多くの研究者が冷や飯を食わされていることをアカデミア時代に身をもって体験していました。
またその領域に投資できるような専門性を持ちつつビジネスに精通した投資家も非常に限られていました。国内で会社設立からスケールアップまで責任をもって取り組める数少ないVCであるジャフコに身を置く以上、「自分がやらなければ誰がやる」と思い、ファージセラピー事業化の検討を始めました。当時、岐阜大学で研究をしながらアステラス製薬に籍を置く安藤さんの話をアカデミア時代の同門研究者から聞き、事業化の可能性を探るために岐阜まで会いに伺いました。
ーその面談ではどのようなコミュニケーションがあったのでしょう。
小林 自分も専門性があるので基本的にはざっくばらんに情報交換をしました。その中で、安藤さんを含む数人のアカデミアメンバーで事業化に向けた定例会議をしていることを共有されたのですが、最終的に「その定例会議に参加しませんか?」と言われました。会った初日に(笑)。
安藤 (笑)。当時アステラス製薬に所属していましたが、企業で扱えるプロジェクトには当然限りがあります。自分では直接扱えないが社会に必要とされるファージセラピーの対象はたくさんあるわけです。これらを自分たちで起業して扱っていく(事業化していく)という選択肢は常に考えていました。ですので、細菌感染症の研究者と投資家としての目線を両方お持ちの小林さんに定例会議に入っていただけたら心強いなと思ったんです。
小林 私も日頃から複数のプロジェクトを抱えており、普段であれば慎重に検討してからお答えするのですが、直感的に安藤さんに強い可能性を感じ、その場で「ぜひご一緒したい」と応じました。そこから定期的にお話しするようになりました。
当時のアステラス製薬との関係に配慮しつつ数年がかりで取り組む覚悟で、定期的に戦略を協議して、新たな仲間を得て、公的資金を獲得して、まだまだ臨床入りまで時間がかかる計画でした。一方で、日本の事業体が単独で感染症の新モダリティ創薬を進められるのか?という肌感もあり、どこかのタイミングでアステラス製薬との連携や臨床アセットの外だしも一つの可能性として想定していました。
ーその後、小林さんの予測が現実になったと。
安藤 はい。2024年の春から1年間、導出活動をしました。さまざまな選択肢がありましたが、最終的にはArrowsmithという会社を設立してそこにプロジェクトを導出することになりました。
小林 直観的な予測より2〜3年早いタイミングだったのですがあくまで想定の範囲内であり、お話をいただいたタイミングですぐにスタートアップ設立に動けました。
売却して現金化や社内でお蔵入りにする選択肢もある中で、「患者さんを助けること」を最優先に安藤さんに技術を託す意思決定をされて、社会貢献への素晴らしい姿勢をもつ会社だと感じました。「ファージセラピー事業化への歩みを止めない」という思いが伝わってきました。
ージャフコがArrowsmithに出資するという具体的な話はいつ出たのでしょうか。
安藤 導出活動を始めてすぐに小林さんが「ジャフコがリードVCとして出資します」と言ってくださったんです。Due diligence(この場合は導出対象の精査)もまだのタイミングで。
小林 そもそも、安藤さんとコミュニケーションする前から本命の一つだった耐性菌の名前が、勤務先との守秘義務の関係もあり安藤さんの口から全く出てこないので、これは逆に取り組んでいるだろうと(笑)。
情報開示が可能になり、初めて説明された時点でハイそこですね、イエス、となりました。きちんとスタートアップ戦略に対応するパイプライン開発を進めて頂いたアステラス製薬の関係者の皆さまに感謝です。また、事前にジャフコのライフサイエンスチーム内で合意の下地を作っていました。
ー臨床パイプライン以外に評価していたことは?
小林 まずはファージ開発の技術に関して、安藤さんは留学中に最先端の人工ファージ研究に従事しましたが、MITは基本的に最先端の工学系大学であり、また、米国は日本と比べて研究システムがとても合理化されています。
少なくとも私がアカデミアにいた時代に日本の細菌学者が現場で取り組んでいたレベルで、細菌やファージの生命現象と地道に向き合える研究者は少ないだろうという実感がありました。安藤さんのように日本で骨太な細菌感染症の研究能力を身に着けてからMITに飛び込んだキャリアだからこそ優れた技術が創り出されたと考えており、グローバルに競争優位性があると感じています。
また、全ての投資に言えることですが、研究・技術をきちんと患者さんに届ける志がある起業家がいるかどうかが重要な投資判断のポイントです。特に研究者には業績が全てという人が一定数います。否定するわけではなく心の在り方の話ですが、業績追及はあくまで自己実現の範疇であり、きちんとしたVCが資金を入れるスタートアップ、すなわち公器を目指す事業を進める上では新たな責任者が必要になります。
とりわけ創薬では、科学技術が発展する前から新薬を必要とする患者さん達がいて、それを治療してきた医師達がいて、これまでも多くの専門家や会社が新たな治療法の開発を試みてきた歴史があり、個々の論文レベルや個人業績だけで患者さんに福音をもたらすことは出来ません。価値ある医薬品候補とは、いろんな人の血と汗とお金が混ざった歴史のバトンを引き継ぎ、多くの専門家が患者さんを治療する目的のために連携して出来上がるものと考えています。
このパイプラインを生み出したアステラス製薬のチームで責任を担い、そして学会や定例会議などを通して仲間や知見をさらに広げていった安藤さんなら、このスタートアップを自ら進めるに足る能力と志があると考えて投資のトリガーが引けると判断しました。
安藤 ありがとうございます。導出活動を始める前からコミュニケーションを取っていたVCは小林さんだけでしたので、すぐに出資の意思を示してくださって嬉しかったです。その後の投資決定もあまりに早くて驚きました。
ー安藤さんがジャフコをリードVCに決めた理由は、小林さんのバックグラウンドや数年かけて築いた信頼関係によるところが大きいですか。
安藤 そうですね。細菌感染症の分野でPhDを取っている日本のベンチャーキャピタリストはおそらく小林さんくらいではないでしょうか。年齢も近いですし、好き嫌いがハッキリしているところも自分と似ていて、最初にお会いしたときから「合うな」と思っていました。
そして、何よりも大きかったのはファージセラピーの根幹にある、薬剤耐性の問題や細菌学の重要性・可能性・難しさを正しく深く理解してくださっていたことです。「小林さんとなら一緒にやっていける」と思えました。
研究者人生を懸けたいと思えた「ファージセラピー」の事業化を着実に進める
ー2025年2月の会社設立、同年5月の投資実行を経て、今後どのように事業を進めていきますか。
安藤 アメリカでの臨床試験に向けて、現在は非臨床データの収集と解析を行っています。2026年の秋頃にIND(新薬臨床試験開始申請)を行い、その後、治験へ進むというのが現在計画しているスケジュールです。実用化までには時間を要しますが、着実に進めていきたいと考えています。また、ここで得られた知見やノウハウを国内に還元し、日本でのファージセラピーの実現に向けた活動も積極的に展開していきます。
経営面での展望で言うと、個人的にはIPOを目指したいと考えています。もちろんM&Aという選択肢もありますが、日本発・日本初のスタートアップという点にはこだわりたく、主体的に関わることができる形を取りたいと考えています。経営陣や、ジャフコさんをはじめとする株主の皆様と相談しながら、状況に応じて最適な選択をしていきたいと思います。
ー安藤さんのように自身の研究の事業化を志す方へ、アカデミア出身の起業家としてメッセージがあればぜひお願いします。
安藤 アカデミアの人間がビジネスの道に進むのは勇気がいることだと思います。アカデミアでは論文を書いたり公的研究費を獲得したりすることが実績になりますが、企業では研究成果を製品として世に出すことが至上命題であり、基本的にこういった活動は二の次になります。得るものも多いですが、アカデミア研究者としての考えが通じなかったり、失うものもあります。
私自身、この道に進んだことでアカデミア研究者として失ったものはたくさんあります。でも、ファージセラピーは私にとって研究者人生を懸けたいと思えるものだった。だから後先考えずに周囲の人たちを巻き込んでここまでやってこれました。
もし、本気でやりたいことがあるなら、思いきって企業に飛び込んだり、ジャフコさんに相談したり、最初の一歩を踏み出してみてください。Arrowsmithは、そのロールモデルとなれるよう全力で取り組んでいきます。
担当者:小林泰良からのコメント
 20世紀の人類最大の発見の一つ、抗菌薬がもたらした乳児死亡率の減少と平均寿命の伸長は現代の人類繁栄の礎となり、特に本邦は優れた公衆衛生環境の寄与もあり細菌感染症は過去のものとして扱われることも少なくありません。一方、海外を中心に安易な抗菌薬乱用などがもたらした多剤耐性菌の出現が多数報告され、WHOも警鐘を鳴らす中で、グローバルな世界に身を置く本邦でもすでに看過できない問題となっています。Arrowsmithはすでに細菌感染症治療薬の開発プロジェクトとしてAMEDの創薬ベンチャーエコシステム強化事業に採択され、本邦の公衆衛生や国防の観点から大きな期待を寄せられています。何より未来の世界中の子供たちを感染症から守る治療手段を確立するため、これまで会社設立に向けて伴走した以上に気を引き締めてジャフコとして最大限支援をしていく所存です。
20世紀の人類最大の発見の一つ、抗菌薬がもたらした乳児死亡率の減少と平均寿命の伸長は現代の人類繁栄の礎となり、特に本邦は優れた公衆衛生環境の寄与もあり細菌感染症は過去のものとして扱われることも少なくありません。一方、海外を中心に安易な抗菌薬乱用などがもたらした多剤耐性菌の出現が多数報告され、WHOも警鐘を鳴らす中で、グローバルな世界に身を置く本邦でもすでに看過できない問題となっています。Arrowsmithはすでに細菌感染症治療薬の開発プロジェクトとしてAMEDの創薬ベンチャーエコシステム強化事業に採択され、本邦の公衆衛生や国防の観点から大きな期待を寄せられています。何より未来の世界中の子供たちを感染症から守る治療手段を確立するため、これまで会社設立に向けて伴走した以上に気を引き締めてジャフコとして最大限支援をしていく所存です。