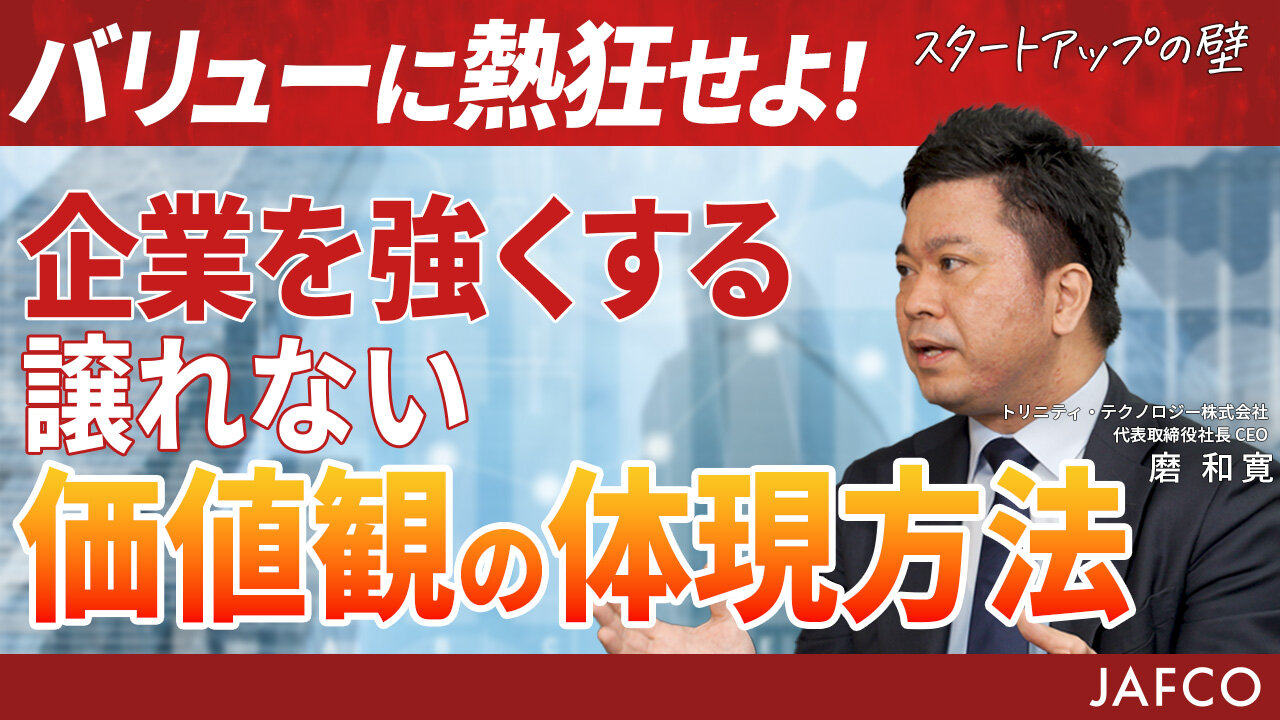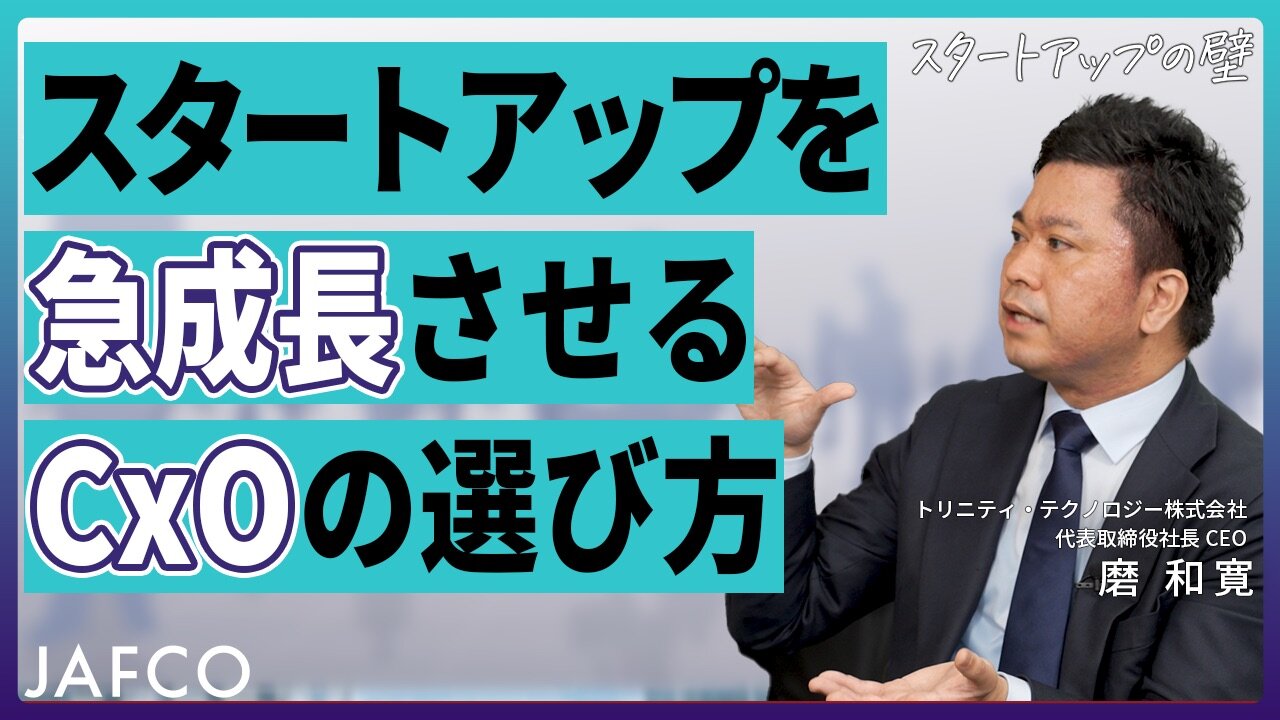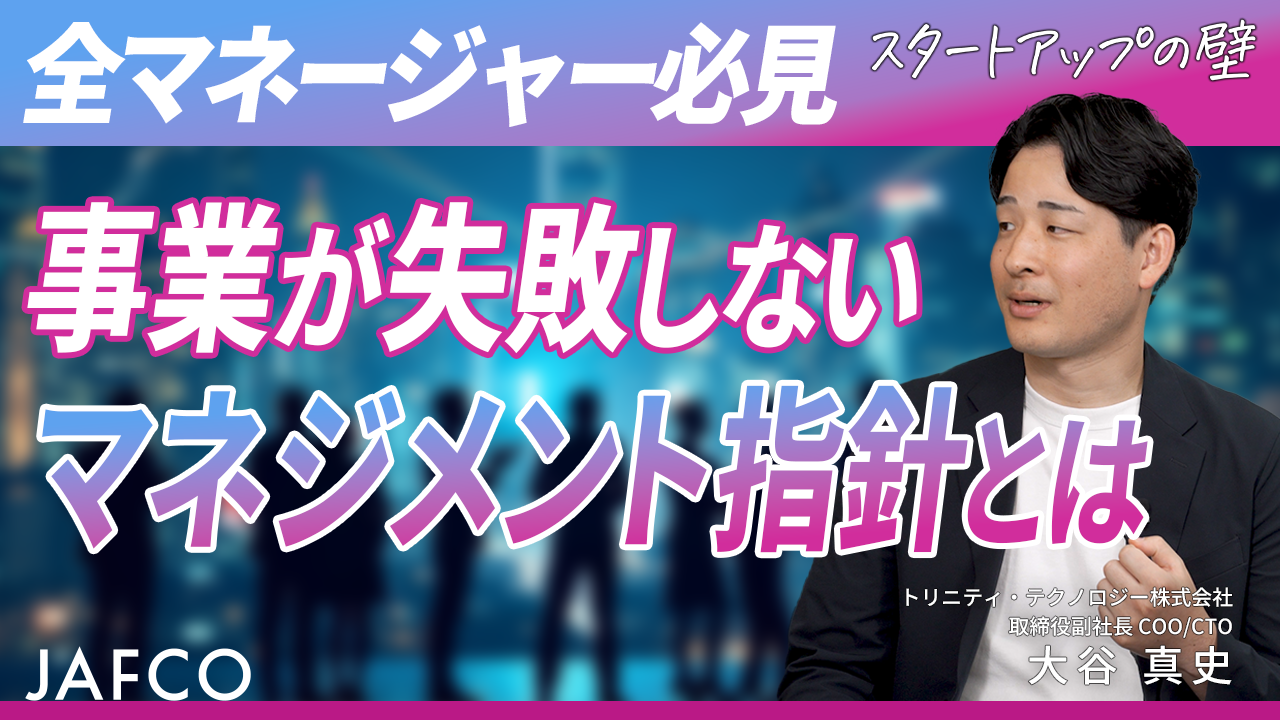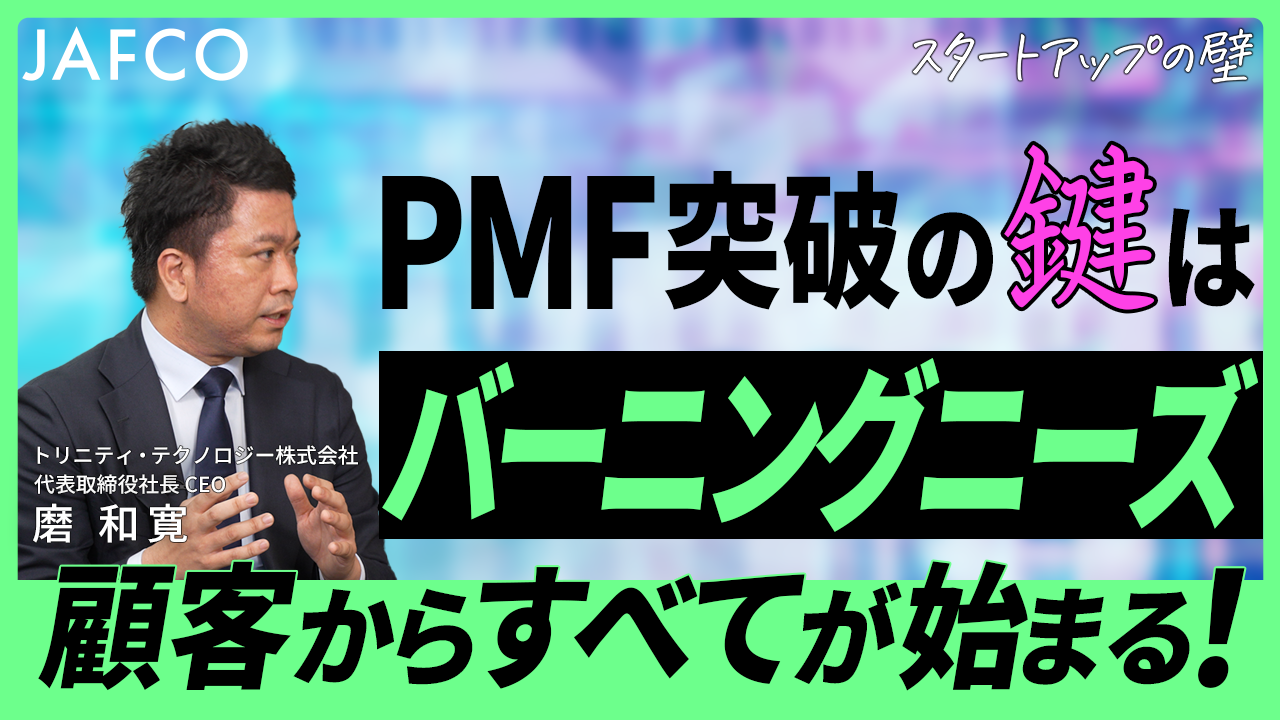【What's トリニティ・テクノロジー?】
トリニティ・テクノロジー株式会社は、「超高齢社会の課題を解決し、ずっと安心の世界をつくる」ことをミッションに掲げる企業です。認知症による資産凍結から親を守る「おやとこ」、家族の代わりにおひとりさま高齢者に寄りそう「おひさぽ」、相続手続きのDX化を実現する「スマホde相続」、専門家ネットワーク「TRINITY LABO.」など、多様なサービスを通じて高齢者と家族の安心を支えています。全国に拠点を展開し、成長を続けています。
創業:2020年10月、従業員数:160名、累計調達額:26億円 / シリーズB調達時
※記載の内容は2025年5月時点のもの
スタートアップの壁 - トリニティ・テクノロジー編。
スタートアップが直面する「壁」について、今回はトリニティ・テクノロジーにお話を伺いました。
これまでに動画でお届けした5つの内容の総集編としてご覧ください。
創業物語
バリューに熱狂せよ!企業を強くする譲れない価値観の体現方法
<出演者> 代表取締役社長CEO 磨 和寛
立教大学法学部卒。2007年司法書士試験合格。
2012年司法書士法人を設立し、国内トップクラスの家族信託の実績を有する士業グループに成長させる。
2020年トリニティ・テクノロジー株式会社を創業。
「第2創業」への決意と社会課題への挑戦
磨社長は、司法書士を中心とする士業グループを約10年間運営した後、「第2創業」としてトリニティ・テクノロジーを設立しました。これは、社会性の高いサービスをより多くの人々に届け、顧客に安心を提供するために、株式上場を目指す「パブリックカンパニー」化を決意したためです。
2020年の創業以来、超高齢社会の課題を解決する5つのサービスを展開しており、特に「おやとこ」は、認知症による資産凍結を防ぐため家族信託の仕組みと資産管理アプリを組み合わせたフラッグシップサービスです。その他、「おひさぽ」「スマホde相続」「従業員承継パートナーズ」「TRINITY LABO.」を提供しています。
会社の経営理念は、「トリニティ」という社名に込められた「三方よし」(売り手よし、買い手よし、世間よし)であり、持続的に人の役に立つための基盤と考えています。
また、ミッションとして「超高齢社会の課題を解決し、ずっと安心の世界をつくる」を掲げており、さらに、ビジョンに「世界一のエイジテックカンパニーになる」を据えることで、「安心」を顧客に届けるうえで、ナンバーワンのブランドであることが重要だと捉えているそうです。
バリューが生み出す究極の価値──価値観を当たり前の企業文化にするしくみ
磨社長は、企業文化の核としてバリュー(価値観)の策定しており、現在は10個のバリューと50個のポリシーを言語化し、実践しています。これは、多様なバックグラウンドを持つメンバー間での価値観や行動基準の共通化を図る目的とのことです。例えば「スピード」というバリューには「ピッパの法則」など、言葉のすれ違いが起こらないためのポリシーが紐づいています。また、バリューの浸透のために、年間表彰「トリニティアワード」や月間バリューアワード、週次ミーティングでの共有、1on1でのバリューの達成度確認など多面的な仕組みを用意しているとのことです。
磨社長は「バリューは売上に直結しないが、経営者自身が信じて体現することが大切」と語り、マネジメント層もその重要性を経験から理解し、広げていくことを重視しているそうです。
また、企業としての本当の強さは日常のオペレーションを徹底、継続することにあり、企業の価値を生み出す源泉となるため、バリューが大事であるとのこと。
スタートアップがバリューを策定する際には、CEOなど最もビジョナリーな人物が、自身の価値観や世界観を偽りなく言語化することが重要だと語ります。また、バリューの実践は「人として正しい」だけでなく、それを体現する人材こそが企業の競争力となるとし、100年先を見据えた長期視点を持つことで、バリューの浸透に本気で取り組めると熱を持って語られています。その詳細や意気込みについては、ぜひ動画をご覧ください。
<ー企業を強くする譲れない価値観の体現方法ー「トリニティ・テクノロジーの創業物語」に関する動画はこちら>
CxO採用の壁
スタートアップを急成長させるCxOの選び方
<出演者> 代表取締役社長 磨 和寛
創業直後のCxO採用の壁と突破戦略
創業当初はCxOが不在で、CTOの必要性は認識しつつも開発は外注を検討していました。しかし、シード期にVCから「考えが甘い」とスタンスを指摘され、優秀なCTO採用の必要性を痛感したそうです。
創業2、3ヶ月で収益・実績ゼロ。全くツテがない中、手探りでのCTO探しを始めるという大きな壁に対し、磨社長は「採用はマーケティングであり営業」と捉え、SNSを駆使して有名企業やスタートアップのCTO約150名をリストアップし、一人ひとりの経歴を研究したそうです。「ブレイクスルーのポイントは熱量である」と信じ、熱意あふれる独自のメッセージで粘り強くアプローチし続けた結果、約10%にあたる15名と面談にこぎつけ、その中で最も優秀だと判断したのが現CTOの大谷氏でした。
大谷氏は卓越した技術力に加え、私がやりたいと思ったことに対して「できるかどうか、いくらで、いつまでに」という事業全体を見通す実務的な視点を持ち、事業そのものへの強い興味関心もあったことが採用の決め手であったとのこと。当初、他社と兼業だった大谷氏に対し、「まずは片足を突っ込むぐらいで」と提案。この柔軟な姿勢と熱意によって、半年かけて本格的なジョインへと導くことに成功しました。初のCxOであるCTO採用ができたことによって、その後のエンジェル投資家やVCからの資金調達を成功させる大きな要因となりました。
CxO採用の哲学と独自の基準
磨社長によると、CxO採用は最初の1人目が最も難しいものの、事業成長やPMF達成、売上増加に伴って採用しやすくなると語ります。まず、採用全般で欠かせないのは、明確な採用基準を事前に定義して置くことだそうです。特に重視する基準は三点あり、第一に、提供するサービスへの「共感性」、第二に「信頼関係」を築けるかどうか、第三に、会社の「バリュー」を実践できる人物かであるとのこと。
さらにCxOについては、特定のスキルセットや過去の経歴に偏らず、「当社の経営パラダイムにインパクトを与え、進化させる存在であるべき」と定義しています。
これは、経営全体を見渡し、新たな視点や専門性をもたらし、既存の経営体制に新たな価値を加えることを意味します。同じ得意分野を持つCxOが複数いても経営にインパクトは与えられないため、新たなカテゴリや専門性を持つ人材が求められるそうです。
磨社長は、今後も経営を進化させるボードメンバーやCMOなど、新たなCxOとの出会いを通じて事業の最大化を図っていきたいと語っています。
共感・信頼・バリューの三基準で見極める、磨社長の採用哲学についての内容は、ぜひ動画をご覧ください。
<ースタートアップを急成長させるCxOの選び方ー「CxO採用の壁」に関する動画はこちら>
マネジメントの壁
「全マネージャー必見 事業が失敗しないマネジメント指針とは」
<出演者> トリニティ・テクノロジー株式会社 取締役副社長 COO/CTO ⼤⾕ 真史
東京⼤学⼤学院⼯学研究科卒。株式会社BuySell Technologies取締役CTO等を経て独立。上場企業からスタートアップまで幅広く社外CTOや技術顧問として活動。2021年に当社取締役CTOに就任、2022年からCOO兼任、2025年から副社長。元トライアスロンアジアJr3位。CTO歴9年目。
マネジメントバリュー策定の背景と狙い
大谷氏は、スタートアップが直面するマネジメントの課題に対し、「マネジメントバリュー」の早期策定と徹底的な浸透によって大きな失敗を回避してきたと語っています。多様なバックグラウンドを持つ社員が増える中で、「有象無象の集団」になるという強い危機感から、会社として「同じ方向を向くため」にマネジメントバリューが必要だと認識し、策定に至りました。これは、創業当初に定めた会社のミッションとバリューが強固だったため、その概念をマネジメントにも応用しようと考えたからこそです。
マネジメントバリューの策定は、アイディア出しから始まり、ボードメンバーやマネージャーからのフィードバックをもとに、「自分たちが大事にしているもの」「こうあるべきもの」「こうありたいと願うもの」という3つの観点から形作られたとのこと。具体的には「メンバーと信頼関係を作る」「達成文化を作る」「現場主義を徹底する」など6つのバリューがあり、会社の状況や目指す方向の変化に合わせて年に1回程度アップデートされているそうです。
「ミニCEO」であるマネージャーを導く3点セットとは
マネジメントバリューは、トリニティ・テクノロジーにとって競争戦略や競合との差別化ポイントそのものであり、アイデンティティや行動指針を形成しているそうです。重要な意思決定のほとんどは、このマネジメントバリューに基づいているとのこと。マネジメントバリューの浸透を促すための取り組みとして、毎週の経営会議の冒頭30分をバリューの振り返りや議論に充てています。また、日常会話でバリューの言葉が自然に出てきたり、Slackのスタンプにバリューが使われたりすることで、浸透を実感しているとのことです。
浸透が進む背景には、磨社長による強い思いからのトップダウンと、マネージャー陣がその重要性を心から理解し信じて行動するボトムアップの両方が機能しているからこそであると語ります。
スタートアップのマネージャーは「ミニCEO」のように多岐にわたる役割を担うため、マネジメントバリューは彼らの「指針」となり、体感や軸がぶれないように助ける効果があるそうです。
大谷氏は、マネージャーのあるべき姿を示すために、定義を分けてとらえ、3点セットとして目的・役割・バリューに分けていたとのこと。
具体的には、目的は、事業を最大化させ、事業を通じてメンバーの幸福を実現すること。役割は、ミッションを事業計画に落とし込み、達成するためのチームを作り責任を持つこと。そしてマネジメントバリューの「3段セット」を明確に定めていたそうです。これから組織拡大をしても、この原則を徹底していく方針であるとのことです。
大谷氏が語る、マネジメントバリューについての詳しい内容は、ぜひ動画をご覧ください。
<ー事業が失敗しないマネジメント指針ー「マネジメントの壁」に関する動画はこちら>
PMFの壁
PMF突破の鍵はバーニングニーズ-顧客からすべてが始まる!
<出演者> 代表取締役社長 磨 和寛
バーニングニーズから始まるN1思考のPMF戦略
磨社長は、スタートアップが直面するPMF(プロダクト・マーケット・フィット)の壁を乗り越える秘訣について、まず「サービスが顧客の真のニーズを満たしていること」、次に「その価値を確実に顧客へ届けられる仕組みを持つこと」、この二段階の達成が重要であると語ります。
同社は超高齢社会の課題を解決するサービス、特に高齢者の財産管理や財産承継の分野で複数のサービスを展開しており、全てのサービスでPMFを達成し、成長軌道に乗せています。最初のフラッグシップサービスであるアプリ「おやとこ」は、必要最小限の機能でリリースされ、売上と利用実績を確認してから本格拡大へ舵を切ったそうです。
この経験から、「バーニングニーズ(顧客が切実に抱えている課題)」を解決するサービスでなければ成功しないこと、「あればいいな」程度のサービスは売れないこと、そしてマーケットの大きさよりも「心から支持してくれるたった一人」がいるかどうか(N1思考)が重要であると熱を持って語られていました。
スタートアップが現場主義と行動力で切り拓く顧客への価値の届け方
磨社長は、PMF達成の鍵として強調するのは、徹底した現場主義と圧倒的な行動量とのこと。実際に現場へ足を運び、顧客と直接対話して得たインサイトこそが真のニーズを見極めるうえで不可欠であり、「恥を恐れずにバットを振り続ける」覚悟を持つべきだと語ります。
さらに、優れたサービスでも顧客に届かなければ意味がないとの考えから、Webマーケティングだけでなく地方銀行とのアライアンス営業にも注力したそうです。地方銀行との提携は困難でしたが、レオス・キャピタル藤野英人氏の「トップダウンではなく現場担当者の共感を得よ」という助言を受け、商品の機能にとどまらず顧客の経済的豊かさや人生の幸せに繋がるストーリーを語ることで提携への扉を開きました。最初の銀行で実績を築くと、3年間で提携行は40行に拡大し、今では銀行側からの問い合わせも増えているそうです。
提携が進んだ背景には、関係性の資産(リレーションシップアセット)の構築と、企業としてのガバナンス体制とコンプライアンス順守が銀行との信頼を得る上で極めて重要でした。
スタートアップは最初「安全な企業なのか」と慎重に見られるため、何度も対話を重ねて信頼関係を築くことが、次の提携につながる"関係性の資産(リレーションシップアセット)"になるそうです。また、銀行側は提携先の体制も重視するため、しっかりとした管理体制(ガバナンス)や法令順守(コンプライアンス)を整えているかが、提携の可否を左右したとのこと。
PMF達成後も磨社長は「会社の成長が単なる膨張になっていないか」「質を伴った成長になっているか」を常に確認し、売上だけでなく顧客に真の価値が届いているかを追い続けているそうです。
徹底した現場主義を貫き、複数のサービスでPMFしてきた事業への向き合い方についての内容は、ぜひ動画をご覧ください。
<ーPMF突破の鍵はバーニングニーズー「PMFの壁」に関する動画はこちら>
未来の壁
ミドルマネージャーが事業を動かす!-「中間管理職」を「中間経営職」へ変える
<出演者> 代表取締役社長 磨 和寛
創業5年の軌跡と「人としての当たり前」が築く信頼関係
磨社長は、トリニティテクノロジー創業からの5年間を「非常に楽しい」時間だったと振り返り、0から1を生み出し、仲間を集めて皆で価値を創造することに喜びを感じていると語ります。
司法書士法人での10年の経験から、ある程度次に起こることの予測がつくようになった一方で、スタートアップの経営は「高速道路に乗っているような感覚」であり、常にスピード感が求められると語ります。この変化の速さの中で、以前は「自分がやればもっと良い成果が出せたかもしれない」と感じることもあったそうですが、次第に「他者に任せる」ことの重要性を認識し、そうした考えを手放せるようになったそうです。
また、「人としての当たり前の徹底」、すなわち挨拶、相手の目を見て話すこと、時間を守ること、約束を守ることといった基本的なことが信頼に繋がり、全ての仕事が人と人とのコミュニケーションや関係性から生まれると信じています。
社員数の増加に伴う文化の維持については、「カルチャーは絶対に濃くしておいた方がいい」と強調し、自ら社員の名前と顔を一致させたり、入社時のミッション・バリュー研修を最大5日間担当したり、年末のトリニティアワードでは社員全員に直筆のメッセージカードを書いたりするなど、フラットな組織を意識して直接コミュニケーションを心がけているそうです。会社のバリューの一つである「人として正しい行いをすること」に基づき、人間の良心や、困っている人を助けたいという心を大切にすることを掲げていると語っています。
事業成長のボトルネックは「採用」にあらず。抜擢人事で育てる中間経営職
今後の事業拡大における未来の壁に対して、磨社長は「社員1000名規模の組織」を見据え、すでに対応可能な組織図を作成していると明かします。そして、この組織拡大における最大の「ボトルネック」は「採用」よりも「ミドルマネージャー(中間経営職)」であると断言しています。これは、ユニクロの柳井正氏が、事業成長の鍵として「店長」の重要性を説いた考え方にも通じるものです。
磨社長は、マネージャーを単なる中間管理職ではなく、数字、業務、ピープル、リスクの4つのマネジメント全てを担う「中間経営職」と位置づけており、特にピープルマネジメントには人間理解のセンスが不可欠だと考えています。この「中間経営職」を育成するため、同社では抜擢人事を積極的に行い、現場で早期に責任ある役割を任せています。実際に、最短で入社2年目、27歳で本部長に就任し、数十名のマネジメントをしている社員もいるそうです。さらに次のステージとして、ミドルマネージャー自身が「新たなサービスを生み出せる」ようになることを目指しており、家系図作成サービス「あいのき」は当時のミドルマネージャーがゼロから立ち上げた実績の一例です。
磨社長個人の目標について、究極の経営は「自分が居なくなっても回り続ける世界を作ること」と語る一方で、「死ぬ瞬間まで挑戦して打席に立ち続けたい」という情熱も持っています。その個人的な挑戦として、現在は「海外展開」を視野に入れているとのこと。これは、「自分には見えているが、世の中の多くの人にはまだ見えていない『歪み』にこそ価値がある」という磨社長の起業家としての信念に基づいているそうです。
会社の成長課題の解決を「採用」ではなく「中間経営職」の育成に見い出す磨社長の経営戦略について、ぜひ動画をご覧ください。
<ーミドルマネージャーが事業を動かす!ー「未来の壁」に関する動画はこちら>
トリニティ・テクノロジー社は、より一層の事業成長に向けて人材採用と組織体制の強化を行っております。
ご興味のある方は、ぜひトリニティ・テクノロジーの採用HPよりご確認ください。
・企業サイト:https://trinity-tech.co.jp/
・採用情報:https://trinity-tech.co.jp/recruit/mid-career/